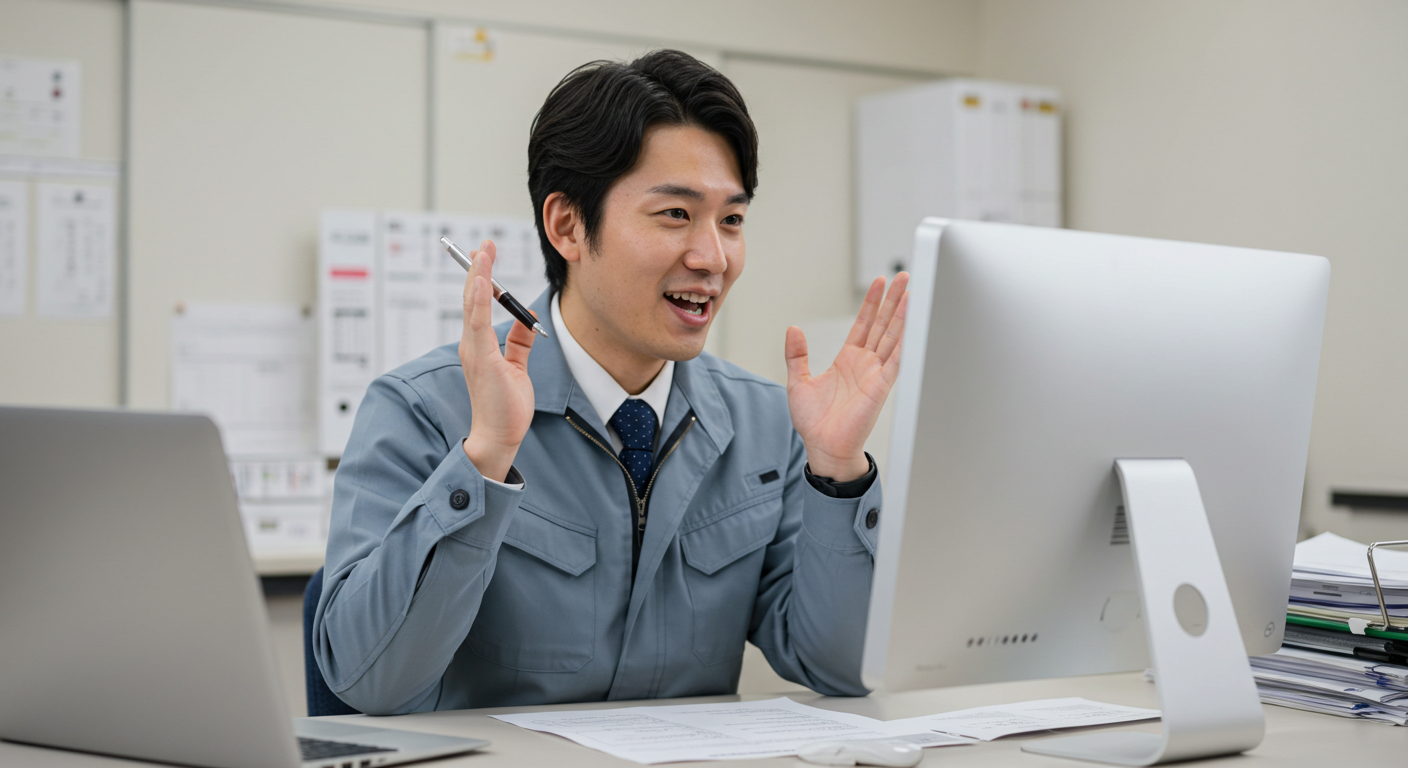こんにちは。愛知県春日井市で機械部品加工を行っている有限会社榊原工機です。
私たちは日々、試作品や少量生産の部品加工を中心に、お客様からさまざまなご依頼をいただいています。その中で何度も直面するのが、「発注側が求める品質」と「私たち加工側が理解した品質」の間にズレが生じてしまうという問題です。
このズレを放置すると、せっかく完成した部品が使えない、作り直しで納期が大幅に遅れる、予算が大きく超過するといった、誰も望まない結果になってしまいます。
今回のブログでは、長年の現場経験から学んだ「品質のすれ違いを防ぐ方法」と「円滑な発注のコツ」を、具体的な事例を交えながらお伝えします。
なぜ品質のすれ違いが起きるのか
部品加工の現場では、図面一枚から製品を作り上げます。しかし、この図面を介したやり取りが、実は品質のすれ違いの大きな原因になっているのです。
設計者の理想と加工現場の現実
設計者の方は、製品の機能を実現するために理想的な形状や厳しい精度を図面に落とし込みます。もちろん、それは製品にとって必要なことです。
ただ、その図面を加工現場で見たとき、「この公差を実現するには特殊な治具が必要だな」「この形状は5軸加工機でないと無理だぞ」「ワイヤーカットで何回も加工しないと出せない精度だ」といった、さまざまな課題が見えてきます。
先日も、こんなことがありました。お客様から複雑な曲面を持つ試作品の依頼があり、図面には厳しい公差が全面に指定されていました。しかし、お話を伺ってみると、その部品で本当に重要なのは一部の嵌合面だけで、他の面は見た目を整える程度で十分だったのです。
結局、重要な部分だけに精度を集中させることで、コストを約30パーセント削減でき、納期も一週間短縮できました。こうしたすれ違いは、決して珍しいことではありません。
暗黙の期待値のズレ
もう一つよくあるのが、「このくらいの価格なら、この程度の仕上げは当然だろう」という暗黙の期待値のズレです。
発注側は「見積もりに含まれている」と思っている仕上げが、実は加工側では「オプション対応」として別料金になっていることがあります。
たとえば、見積書に「マシニング加工一式」と書かれていても、バリ取りの程度、面粗度の仕上げレベル、寸法検査の詳細さなどは、価格によって大きく変わります。
私たちは見積もりの段階で、加工費、段取り費、治具費、表面処理費などをできるだけ詳しくお伝えするようにしています。それでも、細かな仕上げについては実物を見るまで伝わりにくい部分があるのも事実です。
だからこそ、発注の前にしっかりとコミュニケーションをとることが欠かせません。
加工現場のリアルなトラブル
機械加工の現場では、どんなに準備をしても予期せぬトラブルが起こります。
工具が想定より早く摩耗した、材料に予想外の硬い部分があった、加工中にワークがわずかにズレた、といったことは日常茶飯事です。
特に試作や少量生産では、量産品のように加工条件が確立されていないため、こうしたトラブルのリスクが高くなります。
以前、ある材料を加工した際、カタログスペックでは問題ないはずが、実際に削ってみると内部に巣(空洞)があり、急遽材料を変更して対応したことがありました。
こうした現場のリアルを知らないまま発注すると、「なぜ予定通りにできないのか」と不安や不信感につながってしまいます。
私たちのような加工業者は、こうしたトラブルを想定し、経験に基づいて対処していますが、発注者の方にもある程度は加工現場の実情を知っていただくことで、お互いに安心して進められるプロジェクトになります。
試作品の精度が量産の基準になる
品質のすれ違いを防ぐために、私たちが最も大切にしているのが「試作段階で品質の基準を確立する」ということです。
削り出し製品が持つ意味
私たち榊原工機では、自社ブランド「SAKAKI Gear」として、高級ゴルフパター「SAKAKI PUTTER」を製造しています。
このパターは、ステンレスや真鍮の塊から、5軸加工機を使って削り出して作られます。削り出し加工は、素材そのものの密度が均一で、設計通りの極めて高い精度を実現できる製造方法です。
なぜこの話をするかというと、削り出しで作られた試作品は、そのまま「量産時の品質基準」になるからです。
試作品で実現した精度や仕上げを基準にして、「量産ではこの部分は±0.05mmまで許容できる」「この面は機能に影響しないからRa3.2でよい」といった具体的な判断ができるようになります。
曖昧な基準のまま量産に入ると、後から「思っていたのと違う」というトラブルが起きやすくなります。試作段階でしっかりと基準を固めることが、後工程での品質トラブルを大幅に減らすのです。
公差の「なぜ」を共有する
図面に「±0.01mm」と書かれていると、私たちは当然それを実現しようとします。ただ、その公差が本当に必要なのかどうかは、図面だけでは分からないことがあります。
「この穴は圧入するベアリングが入るから±0.01mmが必須です」 「この面はシール材が接触するので、Ra0.8以上の面粗度が必要です」
こうした「なぜその精度が必要なのか」という理由を教えていただけると、私たちは無駄なコストをかけずに、本当に大切な部分に集中して加工できます。
逆に、必要以上に厳しい公差を全面に指定すると、コストが数倍に跳ね上がることもあります。私たち多能工のエンジニアは、設計の意図を理解できれば、「ここは公差を緩めても機能上問題ないので、コストを抑えられますよ」といった代替案を提案できます。
頭を旋盤のように高速回転させて、ベストな加工方法を考えるのが私たちの仕事ですが、そのためには発注側からの情報が欠かせません。
複雑な形状には3Dデータを
最近は複雑な形状の部品が増えています。曲面が多い部品や、内部に複雑な構造を持つ部品などは、2D図面だけでは形状を完全に理解するのが難しいこともあります。
そんなとき、3DのCADデータをいただけると、私たちは加工のイメージをより正確に掴むことができます。特に5軸加工機を使う場合、3Dデータがあれば工具の干渉チェックもしやすく、プログラム作成もスムーズです。
複雑な形状の部品こそ、私たちの腕の見せ所です。ぜひ設計段階から気軽にご相談いただければ、加工のプロとして最適な方法をご提案できます。
納期と特急対応の現実
発注時のすれ違いで多いのが、納期に関することです。「急ぎで」「できるだけ早く」というご要望は日常的にいただきますが、現場には現場の事情があります。
特急対応には工夫とコストがかかる
「来週までに何とかなりませんか」というご相談をいただいたとき、私たちは手持ちの仕事と設備の空き状況を見ながら、どうすれば間に合わせられるかを考えます。
理想は複合加工機や5軸加工機で一気に仕上げることですが、これらの機械が他の仕事で埋まっている場合、マシニングセンタと旋盤を使って工程を分けることもあります。
こうした工程の組み替えには、それなりの手間とコストがかかります。段取り替えの回数が増えれば、その分だけ人件費も設備費もかかるからです。
特急対応をお願いする際は、「通常納期よりもコストが上がる可能性がある」ということを理解していただけると、お互いにスムーズに進められます。
困ったときは電話でご相談を
納期で困ったとき、メールで問い合わせをいただくこともありますが、緊急の場合は電話でご相談いただくのが一番早いです。
実は弊社の社長はお話し好きで、電話で直接事情を伺えば、その場でスケジュールを調整して「何とかしましょう」と対応できることも多いのです。
メールだと返信を待つ時間がもったいないですし、文字だけでは伝わりにくい緊急度や背景も、会話ならすぐに共有できます。
特に試作や少量生産のような案件では、柔軟な対応が鍵になります。困ったときこそ、遠慮なく直接お話しいただければと思います。
一社で完結するメリット
品質のすれ違いは、複数の業者に工程を分けた場合にさらに大きくなります。A社で旋盤加工、B社でマシニング加工、C社で表面処理、といった具合に分けると、工程間の品質引継ぎや納期調整が複雑になります。
私たち榊原工機は、旋盤、マシニング、ワイヤー加工、5軸加工など、多岐にわたる設備を社内に揃えています。金属も樹脂も、焼入れ鋼への追加工も対応できます。
お客様からは「いろいろ相談するよりも榊原工機一社で解決できることが多い」と評価いただいています。一社で完結すれば、品質管理の責任も明確ですし、発注担当者の方の手間も大幅に減らせます。
発注担当者が知っておくべき加工の基礎知識
品質のすれ違いを防ぐには、発注側も加工についての基本的な知識を持っていると、とても役立ちます。
見積もりの内訳を理解する
見積書を見たとき、「加工費」とだけ書かれていると、その内訳が分かりにくいですよね。
実際には、加工費の中には以下のような要素が含まれています。
- 材料費(素材そのものの費用)
- 段取り費(機械の準備や工具の設定にかかる費用)
- 加工時間費(実際に削っている時間の費用)
- 治具費(部品を固定するための専用の道具を作る費用)
- 表面処理費(メッキや塗装などの後処理の費用)
- 検査費(寸法測定や品質チェックの費用)
こうした内訳を理解しておけば、「なぜこの価格なのか」が分かりやすくなり、コスト削減の相談もしやすくなります。
たとえば、「治具費が高いなら、少し納期を延ばして既存の治具を流用できませんか」といった提案もできます。
加工方法の基礎を知る
旋盤、マシニング、ワイヤーカット、5軸加工機など、加工方法にはそれぞれ得意な形状や精度があります。
- 旋盤は円筒形の部品が得意
- マシニングは複雑な平面加工や穴あけが得意
- ワイヤーカットは超精密な内側形状の切り抜きが得意
- 5軸加工機は複雑な曲面や角度のある加工が得意
こうした基礎を知っていると、「この形状ならマシニングで対応できそうだから、5軸加工機を使うより安くなるかもしれない」といった判断ができるようになります。
もちろん、詳しいことは私たちにご相談いただければ、最適な加工方法をご提案しますが、発注者の方が基礎知識を持っていると、話がスムーズに進みます。
トラブル事例から学ぶ
私たちは、マシニングや旋盤、5軸加工機で起きたリアルなトラブル事例を公開しています。
こうした情報は、「こんなことが起こり得るのか」と知っていただくことで、無理な納期やコスト要求を避け、現実的なプロジェクト計画を立てるのに役立ちます。
また、海外調達を検討されている方には、中国調達のリアルな体験談もお伝えしています。品質の不安定さや納期の遅れといったリスクを知った上で、国内の信頼できるパートナーを選ぶという判断もあります。
創造的なものづくりをご一緒に
私たち榊原工機は、単に図面通りに部品を作るだけでなく、「クリエイティブにものづくり」をすることを大切にしています。
ガレージブランドの試作開発支援
個人の方や小規模なブランドが新しい製品を開発する際、試作段階で信頼できる加工パートナーを見つけるのは簡単ではありません。
私たちは、ガレージブランドや個人ブランドの試作開発を積極的に支援しています。
お客様のアイデアを具現化する過程で、技術的な課題を一緒に乗り越え、「こうしたら強度が上がります」「この形状ならコストを抑えられます」といった提案をしながら、最高の製品を作るパートナーとして伴走します。
製品に対する熱意や、市場での価値をしっかりと共有していただければ、私たちも単なる作業者ではなく、創造的な解決策を提供できます。
あたたかい町工場の雰囲気
私たちの会社は、工場っぽくない外観が自慢です。二階の事務所は木の温もりを感じる空間になっていて、初めて訪れる方にも「町工場のイメージと全然違う」と驚かれます。
こうした雰囲気は、お客様が気軽に相談しやすい環境を作るために意識していることです。
技術的な話だけでなく、製品への思いや不安なことも、オープンに共有していただける関係性が、品質のすれ違いを早期に発見し、解消するための土台になります。
部品加工に困ったときは、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
まとめ - すれ違いをなくすための三つのポイント
部品調達での品質のすれ違いを防ぐために、最も大切なのは次の三つです。
第一に、設計の意図や「なぜその精度が必要なのか」を具体的に伝えることです。加工側が背景を理解すれば、無駄なコストをかけずに、本当に大切な部分に集中できます。
第二に、納期やコストについて、現実的な期待値を持つことです。特急対応には追加のコストがかかること、複雑な加工には時間がかかることを理解していただければ、お互いに無理のない計画が立てられます。
第三に、信頼できるパートナーと継続的な関係を築くことです。一社で多くの工程を完結できる業者を選べば、品質管理もシンプルになり、長期的にはコストも納期も安定します。
私たち榊原工機は、試作や少量生産に強い「機械部品加工の駆け込み寺」として、これまで数多くのお客様のご要望にお応えしてきました。
5軸加工、ワイヤーカット、旋盤、マシニングといった多様な技術を駆使し、金属も樹脂も、焼入れ鋼への追加工も対応できる総合力があります。
部品加工でお困りのことがあれば、まずはお電話かメールでお気軽にご相談ください。お客様のプロジェクトを成功に導くために、私たちの経験と技術を全力で提供いたします。